大田黒のドイツ滞在記vol.5~「主な病害とその対策」~
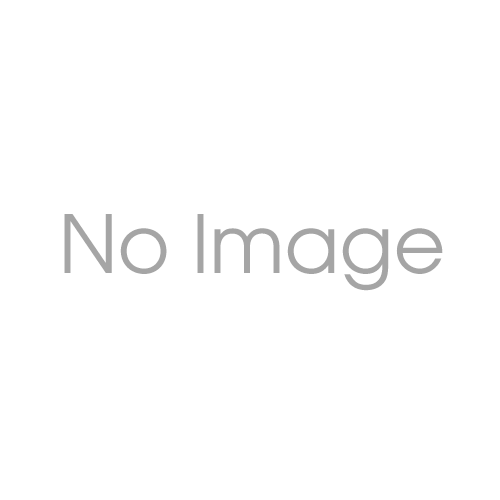.png)
ぶどうの房がなり、大きくなり始める頃ぶどう畑では様々な病害がその姿を表します。
今回は、皆さんも聞いたことのある代表的なぶどうの病害について簡単にご紹介します。
かなり思い切った内容かもしれません。
ご理解ください。
ドイツ現地で他の生産者さんと話す際もよく話題となる病害知名度No.1とも言えるのがペロノスポラ。つまりベト病です。
ベト病はカビ菌によるものです。
カビ菌というくらいですので、主に湿気が原因で葉の気孔に付着、または葉の傷から付着します。


この菌がぶどう自体に付着してしまうとぶどうの実がダメになり、収量減に繋がります。
ただ、気温が30度を超えると活動が落ち着くので暑い夏場には出てきにくいです。
次にオイディウム。うどん粉病です。
ぶどうの房に付着しているのをみつけたら、時すでに遅し。目に見えにくい菌だそうで、一粒見つけたらその房はもう蝕まれている可能性大です。
そして独特のにおいがします。
主にかかりやすい品種が、マスカット系品種やシャルドネ、ピノ・ブランなどです。
葉と実ともに白く粉を噴いたような状態になります。(指で拭うと消える)
とってもありがたくないこの病害たちですが、対策として基本は湿気を溜めないこと。
よくぶどうの周りの葉を取り除いたり、上に伸びすぎた新梢切ったりとが知られていますが、以外に薬剤散布が主な処置となります。
※新梢を切るのも品質向上を目指すのであれば病害とぶどうの成長とのタイミングを慎重に見計らって切らなくてはなりません。
薬剤散布というとこのオーガニックの世の中何言ってんの?と言われるかもしれませんが、絶対に必要な工程です。
*「自然派」と呼ばれる生産者さん(認証を多数持っている)に伺ってもビオで認可されているもので必ず散布するとのこと。とある生産者さんとのお話では品種をPiwi(カビ耐性品種)でも用いない限りは絶対にしなければならないそう。
主な薬剤の内容は以下
・銅
・亜硫酸塩
・カリウム
・マグネシウム
・ココナッツオイル
オイディウムには、ベーキングパウダーも効果的。これはオイディウムの害がひどいと見込まれたときに散布されます。
他にも、私の大敵イラクサでハーブティーを作って畑に巻くことでカビ害対策になります。
ハーブティーの動画はこちらから
※サットラーホフ醸造所のインスタグラムより
あんなに痛い思いをさせておいて役に立つなんてなんて厚かましいやつ!笑
他にもヨーロッパで畑をうろうろするとつい大丈夫か?!これ!となるようなぶどうの葉を見ることがあると思います。

これは、Pockenmilbe (ポッケンミルベ)と呼ばれるカビ菌の一つで、ぶどうが結実した後であれば全く恐れる必要のないものです。
結実前のぶどうの房に付着すると結実不良を起こすことがあります。
何にしても亜硫酸塩を撒くことで簡単に活動しなくなるので全く気にする必要はないです。
かなり心配になる見た目はしてますが。。
最後に有名なエスカの見分け方をお伝えします。
ぶどうに樹が感染して症状が長いもので10年後に表れて一気にぶどうの樹がダメになっていく恐ろしい病気です。
見分け方は以下の写真の通り。
葉には焼けたような茶色、黄色の通称トラ柄の模様が出ます。
また、ぶどうの粒自体に小さな黒い斑点が浮かび上がります。
ご興味のある方以外にはだからどうしたという内容ですが・・・
ぶどう畑で長時間作業するという方は、できればもう着なくなった服等をおすすめします。
僕は、銅のにおいが服の繊維奥深くまで浸透して洗濯しても取れない状態で何着もダメになっていて6着は畑作業用になりました。
色々な難関(私の服も含む)を超えて美味しいワインはできているんですね。。笑
今後も皆さんにへぇーと思っていただけたらいいなと思って配信いたします。
引き続きよろしくお願いいたします。




.png)
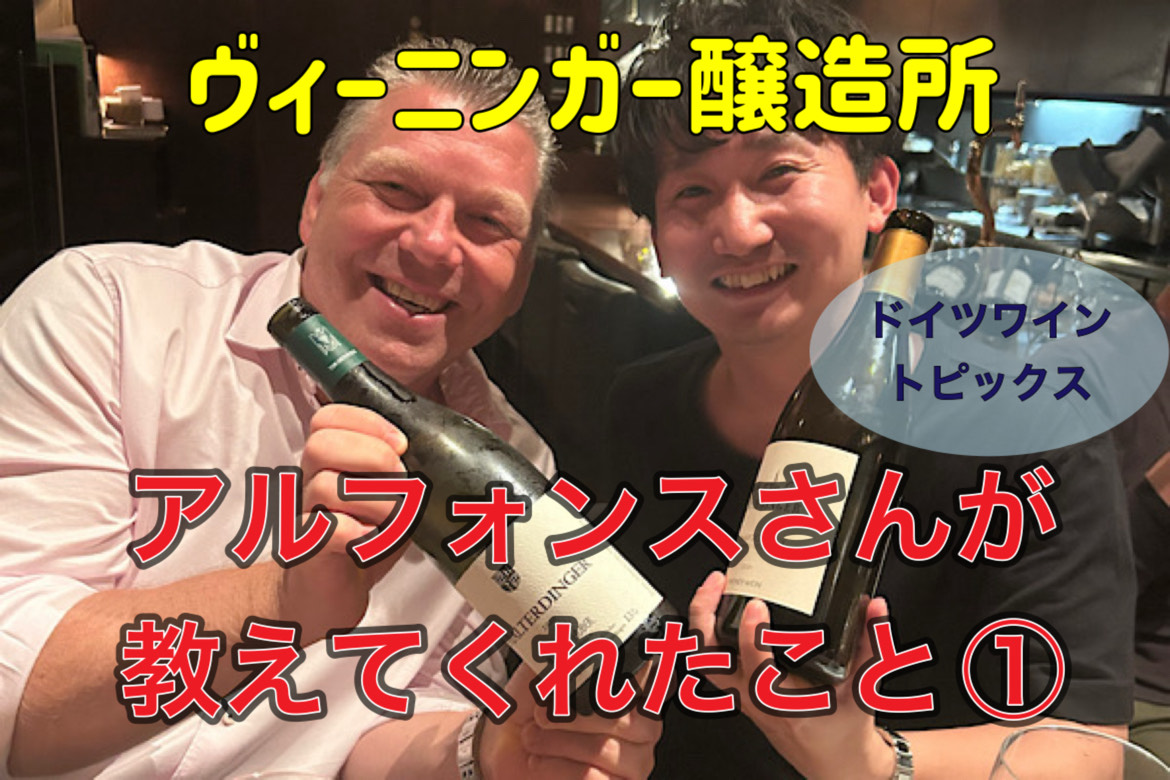
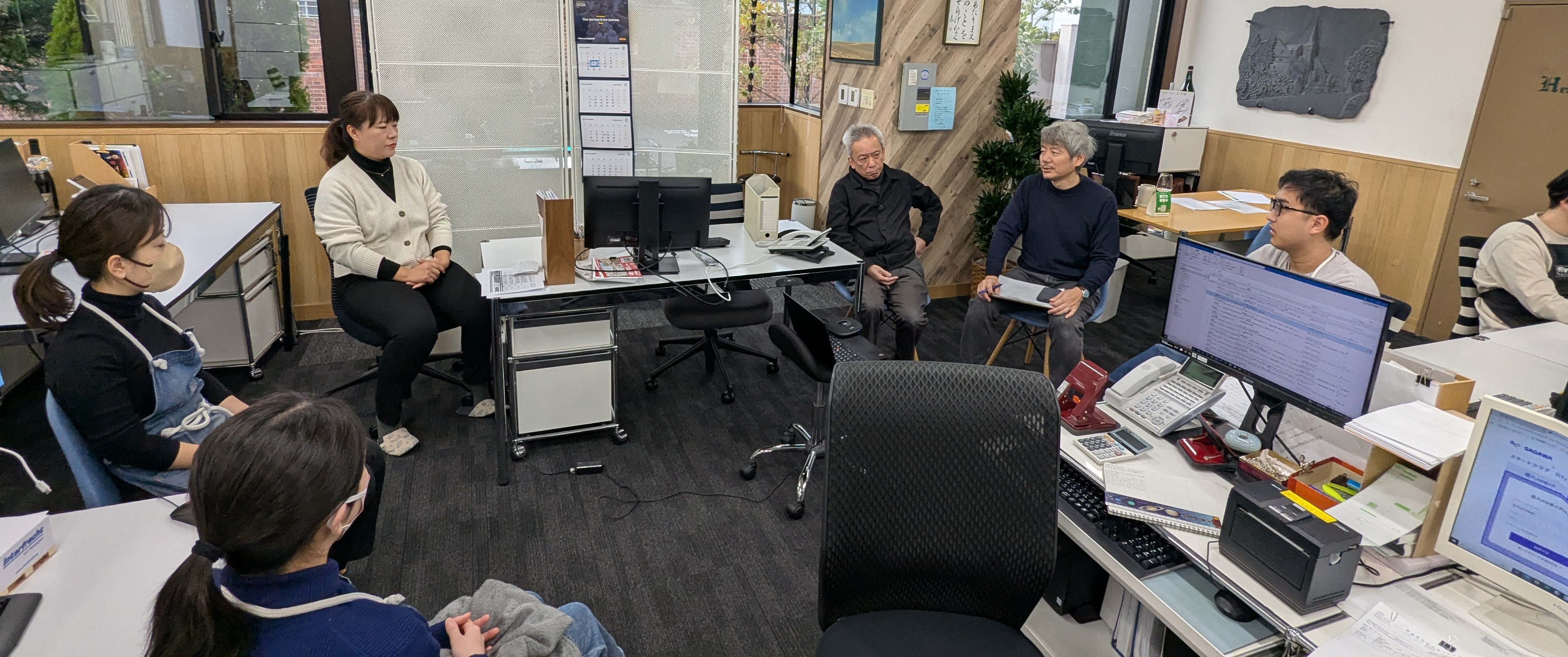
.png)

.png)
