ドイツのグランクリュ(VDP.GG)制定20周年!
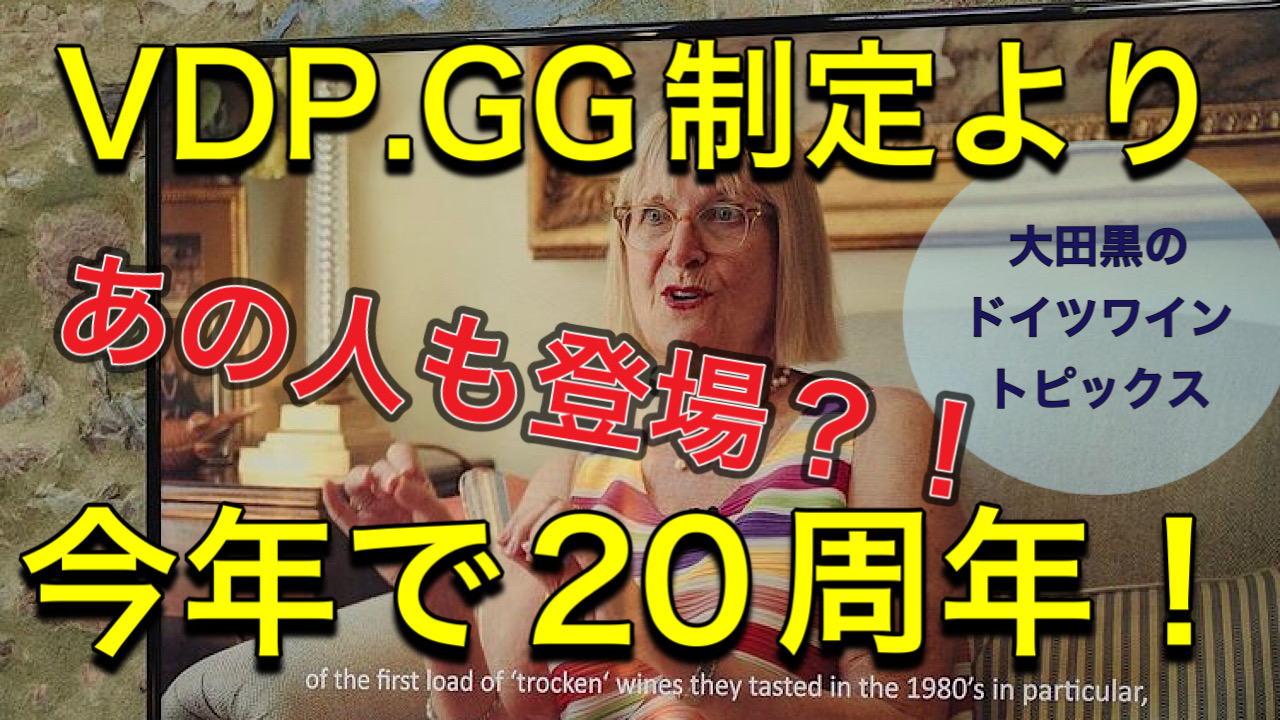
普段、営業活動で様々な酒屋さんや飲食店さんの方とお話させていただく機会のある私ですが、その中でドイツワインについて驚くほど詳しい方とお話しすることもあります。
その際、お互いの話に大きくずれが生じたり、いわば“常識”が全く違っていたりすることもあります。
聞けば、1980年代後半や、1990年代にドイツに行って実際に現地で見てきたという方だったりします。
実はこのずれが生じるのは、至極当然でこの20~30年でドイツワインの状況や、品質には奇跡的といえるほど大きな変化がもたらされました。
大きな変革の中の一つが今回ドイツワイントピックスで触れるVDP.によるGG(グローセスゲヴェックス)の制定です。
今年がドイツのVDP(高級ワイン生産者連盟)によってGG(グローセスゲヴェックス)いわば特級畑名入り表記が制定されて20周年を迎えます。
私のような“GG当たり前世代”(ワインを知り始めたころにすでにGGがあった世代)からすると「え!20年しか経ってなかったの?」と衝撃ですらありますが、この年数がまさにドイツワイン事情が激しく変動した期間を現しているといってもいいでしょう。
2002年に発足したVDP.GGですが、2002年以前(1980年代後半)から辛口への移行や、ピノ・ノワールを中心とした赤ワインの品質向上を打ち出す生産者さんが多くいました。
しかし、当時はそれぞれの醸造所が決めた独自のルールでワインを打ち出していました。
それらのワインに一定の基準を設けて、高品質のワインがどんなクラスのどこの畑から、どのくらいの収量と手間をかけ、一定の品質以上でかつ辛口あるということを消費者に対して明確化したものがVDP.GGです。
これは、あくまでVDP.という現在約200の生産者が加入する1団体での決まりで、VDP.加入醸造所以外には適応されない決まりです。
しかし、2026年から適応される新ドイツワイン法のベースとなったのがこのVDP.の規則です。
※新ワイン法に関しては、第4回ドイツワイントピックスをご覧ください。
http://www.herrenberger-hof.co.jp/blog/2021/05/12/484
ワイン法のベースとなるほどの規則を一体誰が作ったのか。
実はGGの命名には、ヒュー・ジョンソンやマイケル・ブロードベントなどの著名人が携わっています。その後のGGの名が広がり現在は世界中でグランクリュ(特級)として認識されます。
しかし、この規則の発案者にして実行人の一人がまさに我らがゲオルグ・ブロイヤー醸造所の前当主ベルンハルト・ブロイヤーさんです。
現在VDP.からは脱退しているゲオルグ・ブロイヤー醸造所ですがその功績もあり、GG制定20周年を祝したGGの先行試飲会での特別祝賀会で現在の当主テレーザ・ブロイヤーさんが登壇する一幕がありました。

当時、ゲオルグ・ブロイヤー醸造所がVDP.を自ら脱退した理由としては、ベルンハルトさんが提唱したGG既定の収量制限が厳しすぎ、当時の他のVDP.の生産者さんが反対したため、そしてノンネンベルク畑が急斜面で川沿いではないという理由だけでVDP.のGGに認められなかったためでした。
それほどまでに品質に対して、熱意をもち人生をかけて取り組まれた結果が世界中のワインファンにGGの名が知られ、法律まで変えるほどの影響力をもつ規則を作りえたのかもしれません。
今回この祝賀会に呼ばれ登壇し、挨拶をしたのはテレーザさん。
VDP.に再加入を発表したわけではなくVDP.がお父さんのベルンハルトさんの功績を称えてとのことでしたが、以前、テレーザさんがVDP.に再加入はあるか?という「質問にもし機会があれば」というような返し方をしていました。(どこで言っていたか忘れてしまいましたが・・・)
もしかすると、VDP.に再加入がニュースとなる日も来るのかもしれません。
ドイツワインは、たった20年でここまでの変化をとげたので今後の20年もさらに楽しみです。
いよいよ国が認めるワイン法も施行されたり、VDP.でゼクトの規定が新しく設けられたりとまだまだ変革の止まらないドイツワイン。今後が楽しみです。
※ゼクトの規定も第1回ドイツワイントピックスで解説しています。
http://www.herrenberger-hof.co.jp/blog/2021/02/10/436
◆今回のドイツワイントピックスでお伝えしたいこと◆
・VDP.GGが今年で20周年!
・ドイツワインは、まさにこの約20年での品質改革が目覚ましい
・今後の発展にも期待大!
おまけ:
今回の20周年の祝賀会の際に映り込んだ弊社取り扱いの生産者さんたちの写真をお届けします。中にはオーストリアからのビックゲストも!しかも、どうやら大御所席に・・・。






.png)
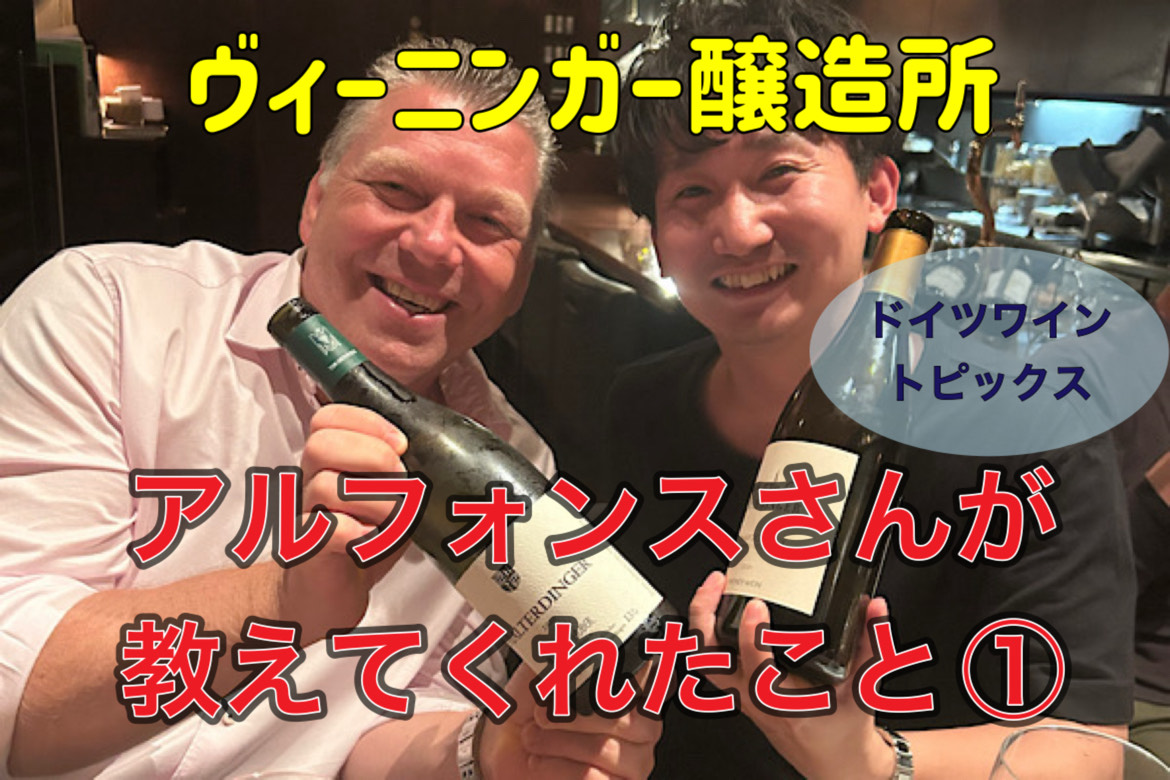

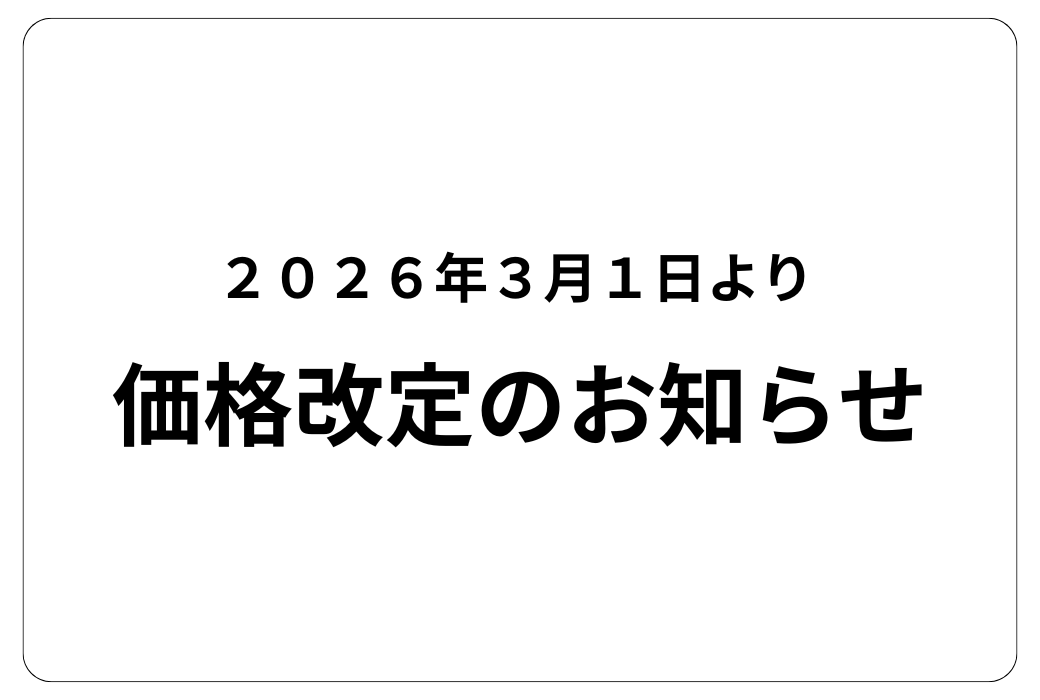

.png)